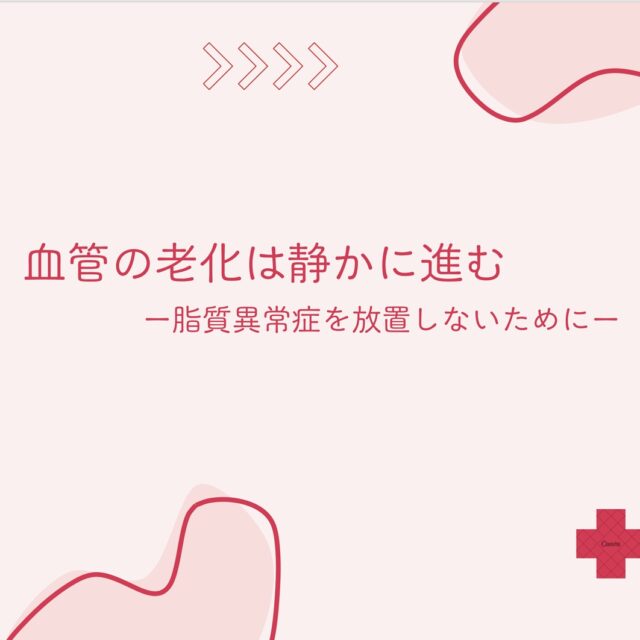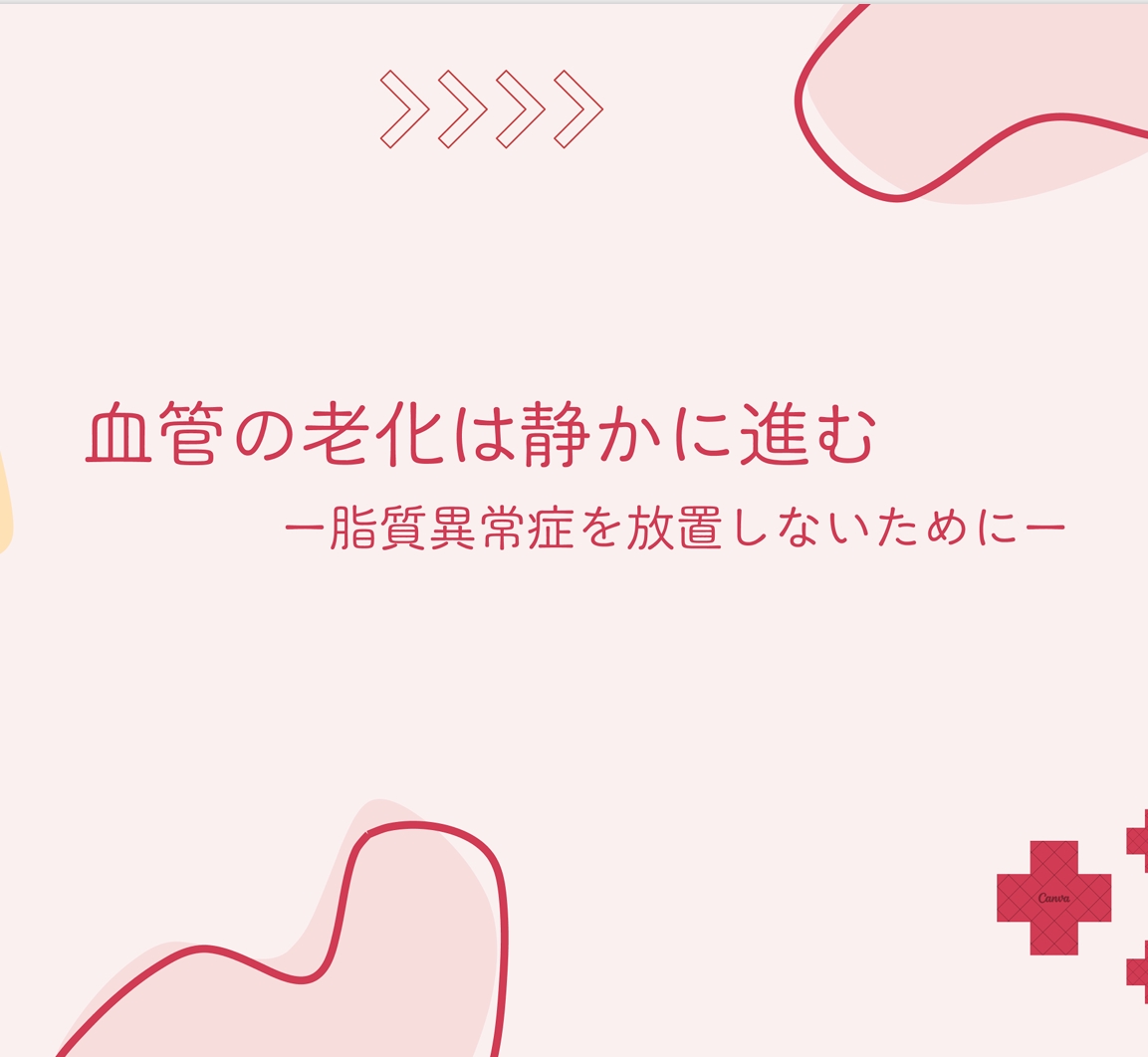今月の生活指導のテーマは【高血圧症について】です。
→上記リンクからPDF形式でもご覧いただけます。
① 高血圧症とはどのような病気か?
血圧とは、心臓が血液を全身へ送り出すときに血管の壁にかかる圧力のことです。
血圧には「収縮期血圧(上の血圧)」と「拡張期血圧(下の血圧)」の2つの数値があります。上の血圧は心臓が収縮して血液を送り出すときの圧力、下の血圧は心臓が拡張して血液をためているときの圧力を表します。
日本高血圧学会が2024年に発表したガイドライン(JSH2024)では、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の状態を「高血圧」と定義しています。
高血圧の最も大きな問題点は、ほとんどの場合、自覚症状がないということです。例えば、風邪のように熱が出たり咳が出たりするわけではありません。そのため、自分では気づかずに長期間放置されやすく、知らないうちに体の中では血管に強い圧力がかかり続けています。
この状態が続くと、血管の内壁が傷つきやすくなり、そこにコレステロールなどの脂質が入り込んで「動脈硬化」が進行します。動脈硬化とは、血管が硬くもろくなり、内側が狭くなってしまう現象で、これが進むとさまざまな命にかかわる病気の引き金となるのです。
つまり、高血圧は「ただの数字の問題」ではありません。「血圧が高い」という状態は、全身の血管にストレスがかかっているというサインであり、将来的な重大疾患(脳卒中や心筋梗塞など)への入り口でもあります。
② 高血圧を治療・管理する意味
では、なぜ血圧を下げなければならないのでしょうか。
その理由は、高血圧が長く続くと、心臓や脳、腎臓といった生命維持に関わる重要な臓器に深刻なダメージを与えるからです。
● 心臓への影響
血圧が高いと、心臓はより強い力で血液を送り出さなくてはなりません。これが続くと、心臓の筋肉(特に左心室)が厚くなり、「左室肥大」と呼ばれる状態になります。これは心不全や不整脈の原因となり、最悪の場合、突然死につながる危険性もあります。
● 脳への影響
高血圧は、脳卒中の最も強い危険因子です。脳の血管は細くて繊細なため、高い血圧により破れやすくなり、**脳出血(血管が破れる)や脳梗塞(血管が詰まる)**を引き起こします。特に高齢者では、ちょっとした血圧の上昇でも命に関わる重大な後遺症を残すことがあります。
● 腎臓への影響
腎臓には、血液をろ過して尿をつくる「糸球体」というフィルターのような構造がありますが、高血圧はこのフィルターを徐々に破壊していきます。その結果、**慢性腎臓病(CKD)**が進行し、最終的には人工透析が必要になるケースも珍しくありません。
しかし、適切な治療によって血圧をコントロールすれば、これらのリスクを大きく減らすことができます。
2015年に発表された国際的な臨床研究「SPRINT試験」では、収縮期血圧を120mmHg未満にコントロールしたグループでは、心血管イベント(心筋梗塞・脳卒中など)と死亡のリスクが25~30%も低下したという結果が出ています。
つまり、高血圧を「放置しない」ことが、命を守ることにつながるのです。
③ 放置するとどうなるのか?―「沈黙の殺し屋」の恐怖―
高血圧が恐ろしい理由は、「症状がないままに、確実に体を壊していく」点にあります。
そのため、医療現場ではしばしば高血圧のことを「沈黙の殺し屋(サイレントキラー)」と呼びます。
たとえば、こんな病気を引き起こします。
● 脳出血・脳梗塞
脳の血管が破れる、あるいは詰まることで起こります。
発症すると、突然の片麻痺、言語障害、意識消失などを起こし、命に関わるだけでなく、その後の生活に重い後遺症が残ることもあります。
● 心筋梗塞・狭心症・心不全
心臓の冠動脈(血管)が高血圧でダメージを受け、詰まったり破れたりすると心筋梗塞になります。これは突然死を引き起こす代表的な疾患です。
また、心臓のポンプ機能が低下することで、息切れや浮腫(むくみ)が出る「心不全」も起こります。
● 慢性腎臓病(CKD)→人工透析
高血圧が腎臓の血管を損傷させ、徐々に腎機能を低下させます。これが進行すると、自分の腎臓で老廃物を排出できなくなり、人工透析が必要な状態になります。
これらの合併症は、一度発症すると完全に元の健康状態に戻ることが難しい場合がほとんどです。
だからこそ、何よりも重要なのは「発症を防ぐこと=血圧を下げておくこと」です。
「今は何も症状がないから大丈夫」と思っていても、それはあくまでも「静かに進行しているだけ」にすぎません。
「少し高め」と言われたときこそが、将来を守る最大のチャンスです。
あなたの体は、静かに助けを求めているかもしれません。
④ 高血圧の治療にはどんな方法があるの?
高血圧の治療は、「生活習慣の見直し」と「薬による治療」の2本柱で進めます。どちらか一方だけでは不十分なことが多く、両方をバランスよく行うことが重要です。
<生活習慣の改善:治療の“土台”です>
高血圧の治療において、最初に取り組むべきなのが「生活習慣の見直し」です。特に日本人にとって大きな課題となるのが、塩分の摂りすぎです。
・減塩:1日の塩分摂取量を6g未満に抑えることが推奨されています。これは、ラーメンのスープを飲み干すと1杯で6gを超えてしまうほどの量です。
・体重管理:体重を5kg減らすだけでも血圧が5〜10mmHg下がることがあります。
・定期的な運動:ウォーキングなど軽い有酸素運動を週に3〜5回(1回30分程度)行うことが勧められます。
・節酒:男性で日本酒1合、ビール中瓶1本程度が上限とされています。
・禁煙:たばこは血管を収縮させ、動脈硬化を進めるため、高血圧の方にとって禁煙は最重要です。
<薬による治療:必要なときに、必要な量を>
生活改善だけでは十分に血圧が下がらない場合や、合併症リスクが高い方には、降圧薬の使用が必要です。
・カルシウム拮抗薬:血管を広げて血圧を下げる。最もよく使われる薬のひとつ。
・ARB/ACE阻害薬:血圧を下げながら腎臓や心臓を守る。糖尿病・腎疾患がある方にも適応。
・利尿薬:体内の余分な水分・塩分を排出して血圧を下げる。高齢者にも有用。
・β遮断薬:心拍数を抑え、心臓の負担を軽減。不整脈や心疾患に適応。
最近の降圧薬は副作用が少なく、毎日服用することで脳卒中や心筋梗塞の予防効果がはっきりと証明されています。
⑤ どうして生活習慣の改善がそれほど大切なの?
薬で血圧は下がりますが、生活習慣の改善こそが根本的な対策です。薬だけでは生活習慣に起因する高血圧を完全に制御することはできません。
<高血圧の背景にある「生活習慣病」という現実>
高血圧の多くは、食生活・運動不足・ストレスなどが原因です。生活習慣が変わらなければ、薬をやめたとたんに血圧が再上昇する可能性があります。
<生活改善のメリット>
・降圧薬を減らしたり中止できる可能性がある
・糖尿病や脂質異常症など他の生活習慣病の予防にもつながる
・健康寿命が延びる
生活習慣の改善はすぐに結果が出るものではありませんが、小さな積み重ねが将来の大きな成果につながります。日々の習慣があなたの血管を守ります。
⑥ 毎日の生活でできる工夫とは?
高血圧の治療を継続するには、日常生活の中で無理なく実践できる工夫がカギとなります。<日常生活での5つの工夫>
1. 毎日決まった時間に血圧を測る
朝起きた直後や就寝前など、リズムを決めて記録を習慣にすることで体調の変化にも気づきやすくなります。
2. 減塩料理の工夫
酢・レモン・香辛料・だしのうま味を活用して、塩分に頼らず美味しく仕上げることができます。
3. 外食やコンビニ食の選び方
スープやソースを残す、塩分の多い漬物や加工食品は避けるなど、意識するだけで摂取量を大きく減らせます。
4. ストレスをためない・発散する
ウォーキング・読書・音楽など、自分なりのリラックス法を見つけましょう。血圧はストレスにも敏感です。
5. 完璧を目指さず「できることから」
生活改善は“継続”が第一。80点でも十分です。
無理なくコツコツ続けていくことが成功のカギです。